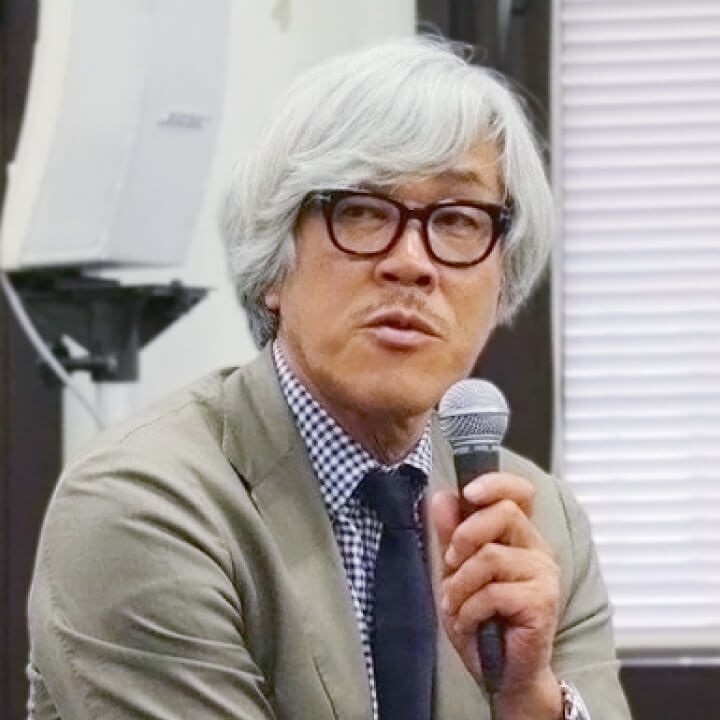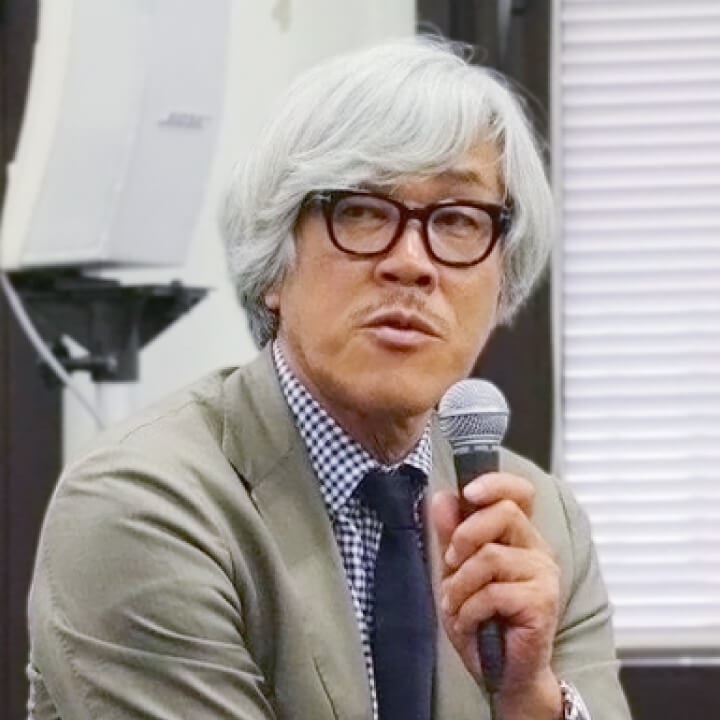関連する記事
-
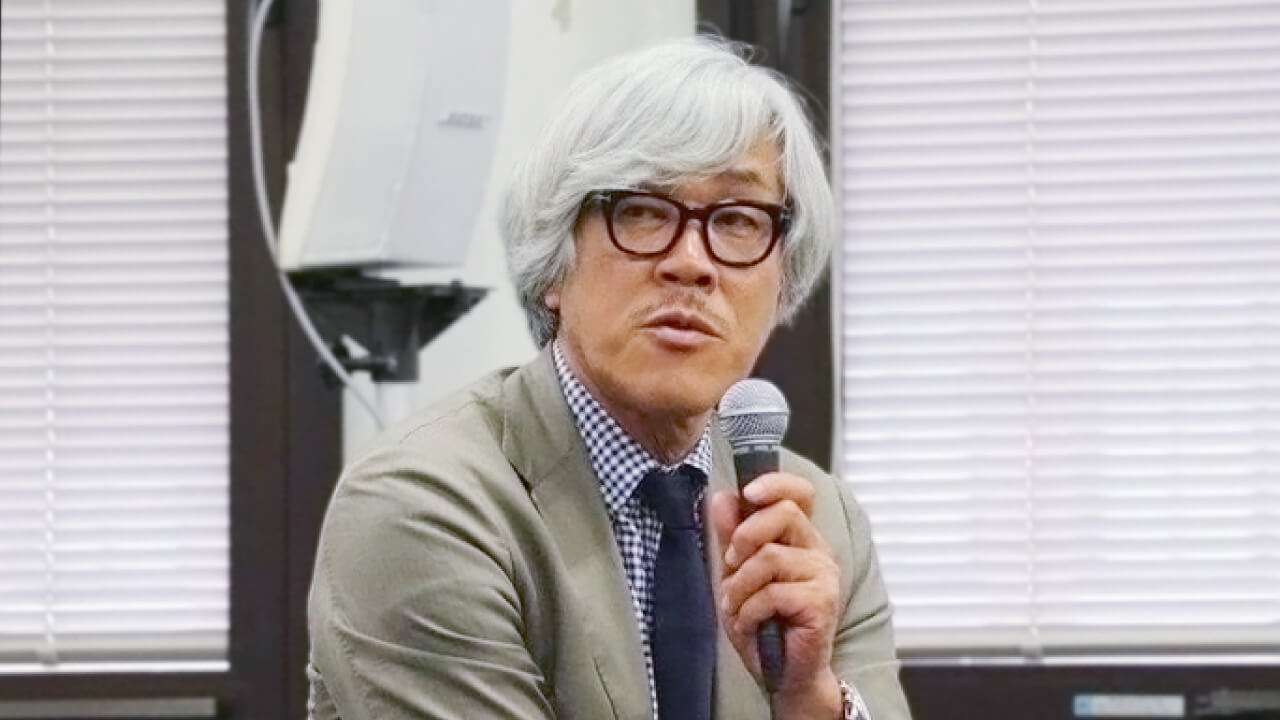
松下直樹のスポーツの進化:スポーツの価値って、いったい? する、みる、支える
2023/07/12
-

ホークスを伝え続けて18年。「選手とファンの心を掴む術」
2023/04/18
-

その他注目記事
-

-
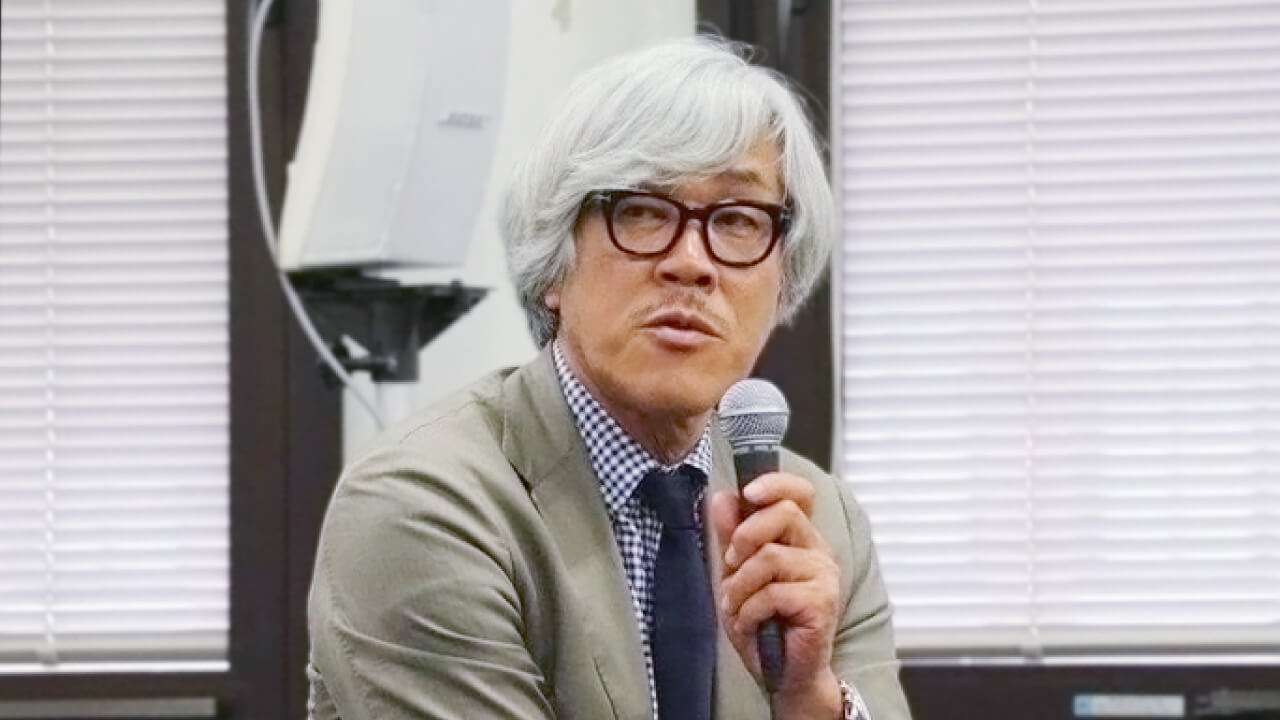
松下直樹のスポーツの進化:スポーツの価値って、いったい? する、みる、支える
2023/07/12